自治体必見!自動車税の課税事務に使える証紙代金収納計器の特徴
自動車税や車検登録時にかかる手数料などは都道府県へ納付する必要があります。この際、収入証紙とよばれる切手のようなものを購入して書類へ貼り付けることもあります。
しかし、膨大な証紙を処理する自治体や公共団体にとっては手間がかかり、ミスも起こりやすいものです。また証紙を紛失、盗難等のリスクも考えられます。そこで、「証紙代金収納計器」とよばれる専用の機器を使用することで証紙の処理や管理が大幅に効率化できます。
証紙代金収納計器とは
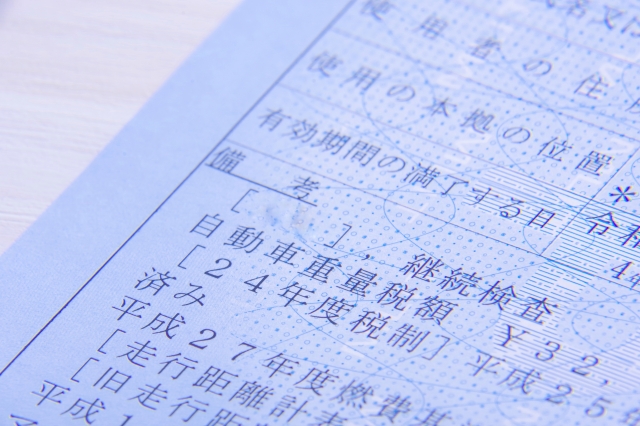
証紙代金収納計器とは、自治体などで発行される収入証紙を処理するための機械です。
収入証紙と似たものに収入印紙がありますが、印紙とは国に納める税金や手数料として使われるのに対し、証紙は地方自治体に収める税金や手数料として用いられます。
収入証紙を取り扱うシーンとして代表的なのは、主に自動車重量税や自動車取得税、車検の登録手数料などの支払いです。
これらは通常、収入証紙を購入してきて書類へ貼り付けて申請しますが、証紙代金収納計器があれば証紙を購入・貼り付ける手間がなくなり、業務効率化につながります。
収入印紙は契約書や領収証など、日常の取引で使用する書類に貼り付けることが多いのに対し、収入証紙は自動車税や手数料の支払いなど使用するシーンが限られています。そのため、印紙税納付計器は一般企業でも導入するケースが多いですが、証紙代金収納計器の場合は主に自治体や公共団体などで利用されるケースがほとんどです。
ちなみに、証紙代金収納計器は不正利用ができないよう厳重に管理する必要があることから、専用のカードを差し込まないとシステムへのログインや料金の書き込みができないセキュリティ対策が施されています。
自動車税・自動車取得税の課税事務の流れ

証紙代金収納計器の活用によって得られる効果やメリットを理解するためには、その前段として自動車の税金に関する課税事務を把握しておくことが大切です。
今回は軽自動車の課税事務を例に、証紙代金収納計器を使った一連の流れを解説しましょう。
- 自治体が全国軽自動車協会連合会の各取扱所を証紙代金収納計器取扱人として指定
- 始動標札の購入
- 代行業者等から取扱所へ税相当額を支払い
- 取扱所は証紙代金収納計器で申告書へ収納印を押印
- 取扱所から自治体へ申告書を提出
- 取扱所から自治体へ計器使用状況を報告
ちなみに、普通車の場合は国(運輸支局)へ自動車重量税や検査・登録手数料を印紙納付し、自治体には自動車取得税と自動車税を納付します。その後、自治体は代行業者等に対して納税済証を、運輸支局からはナンバープレートが発行されます。
証紙代金収納計器が活躍するのは、証紙を取り扱う自治体および関連団体などであり、膨大な量の証紙の事務処理を効率化することができます。
証紙代金収納計器の導入メリット
証紙代金収納計器を導入することによって、課税事務を担う自治体などはどういったメリットを得られるのでしょうか。
業務効率化
証紙代金収納計器は、取り扱う証紙の量が多いほど事務作業を効率化できます。従来であれば手作業で収納印の押印や証紙発行の集計が必要であったものが、証紙代金収納計器があれば課税事務の一部自動化が実現でき、人件費の削減につなげられるでしょう。
セキュリティの向上
証紙代金収納業務にあたっては、第三者の不正なログインや操作によって、不正利用につながるおそれもあります。
しかし、証紙代金収納計器は、システムへのログインには専用のカードが必要なほか、料金を書き込む際には専用の認証カードが必要など厳重なセキュリティ対策が施されています。
これにより不正利用を未然に防止でき、正確な課税事務の遂行をサポートします。
始動標札の正確な管理
証紙代金収納計器を使用する際には、始動標札をあらかじめ購入し、そこから課税金額に応じてチャージされた分を差し引くという処理が行われます。
始動標札には膨大な金額が記録されるため、正しい管理を行っていないと経理の処理において間違いが生じることがあります。
証紙代金収納計器では、始動標札専用カードも用意されているため、第三者が不正に始動標札を利用したりデータを書き換えたりといったリスクも防げます。
自動車税以外でも証紙代金収納計器は使える?

収入証紙は特に自動車税や車検取得にかかる事務手数料など、自動車に関連するユースケースが多いため、特に自治体の自動車税事務所や軽自動車協会などで多く利用されるケースがあります。
しかし、そもそも証紙代金収納計器は自動車関連の税に限定したものではなく、収入証紙を取り扱う組織や団体であれば幅広く活用できます。
収入証紙の代表的な利用例としては、運転免許試験の申請や運転免許証の交付にかかる手数料納付のほか、公立高校の受験料納付、教員免許の申請にかかる手数料、さらには粗大ごみの収集費用など多岐にわたります。
そのため、これらのように収入証紙を頻繁に取り扱う事業所では証紙代金収納計器を導入することで大幅な事務作業の効率化が見込めるでしょう。
SH-2021 証紙代金収納計器の特徴

https://mail.quadient.com/ja/sh-2021
証紙代金収納計器の導入先はほとんどが自治体や公共団体などに限られているため、製造・販売しているメーカーも多くありません。
現在、多くの自治体に納入されている製品が、クアディエントの「SH-2021 証紙代金収納計器」です。
SH-2021 証紙代金収納計器の概要
証紙を処理する本体部分の基本端末と、操作用のインターフェースと処理内容や情報を表示するディスプレイ部に分かれており、ディスプレイ下部にはセキュリティを強化するためのカード読み取り装置があります。
本体サイズは基本端末部分が幅370mm、奥行280mm、高さ430mm、ディスプレイ部が幅420mm、奥行335mm、高さ273mmとなっており、オフィスに設置していても邪魔になりにくいサイズ感です。
大型のタッチパネルを採用
SH-2021 証紙代金収納計器は大型の12インチディスプレイを採用しているため視認性が良く、タッチパネルで直感的な操作もできるため機械が苦手な方でも安心して操作できます。
充実したセキュリティ機能
SH-2021 証紙代金収納計器を利用するためには、システムログインに使用する専用のカードと、料金を書き込むために使用する認証カード、そして始動標札用のカードがあり、それぞれの用途に応じてカードリーダーにかざして使用します。
カードがなければ操作ができない仕様となっているため、万が一機器が盗難や紛失した場合でも不正利用を防ぐことができます。
高い処理性能
SH-2021 証紙代金収納計器は1分あたり16枚の証紙を処理でき、静音設計のため動作中もオフィス内で騒音が気になることがありません。
また、これまで発行した収入証紙の履歴と集計も簡単にでき、収入証紙に領収印を印字する際には手差し印刷で確実に処理ができます。
まとめ
自治体への税金や手数料の納付に使用する収入証紙は、近年一部の自治体で廃止の動きが見られます。その代わりに現金での納付は今後増えてくると考えられ、証紙を処理する自治体においてはさらなる業務効率化が求められるでしょう。
証紙代金収納計器は証紙を適正かつスピーディーに処理するための効果的なソリューションであり、特に自動車関連の税金を扱う部署や団体におすすめです。
クアディエントのSH-2021 証紙代金収納計器は、これまで数多くの自治体へ導入実績があるため、ぜひこの機会にご検討ください。
2019年、消費税率の改定とともに郵便料金も値上げされたことをご存知でしょうか。
はがきや定形郵便などは数円の値上げですが、わずかでも切手が不足していると料金不足によって正しく配達されない可能性もあります。
そこで今回は、改定後の郵便料金はいくらになったのか、一覧で紹介するとともに、郵便物の料金が不足していた場合どう対処すれば良いのかについても解説します。

郵便料金はいつ改定された?

郵便料金はこれまで、さまざまな理由によって改定されてきました。
直近で変更となったのは2019年10月1日で、消費税率が8%から10%へ引き上げとなったタイミングに合わせて実施されました。
従来と比べてどの程度の値上げとなったのか、郵便料金改定後の価格について紹介するとともに、今後郵便料金が改定される予定はあるのかについても詳しく解説しましょう。
▶︎クアディエントの郵便料金計器で総務や経理のお悩みを解決!詳細はこちら
郵便料金改定後の価格一覧

2021年7月現在、ハガキを差し出す際には63円、封書の場合は84円の切手を貼る必要があります。
現在の郵便料金は2019年10月1日から改定されたもので、それ以前はハガキが62円、封書が82円でした。
また、その他にも定形外郵便や速達、書留などの料金についても値上げされています。
今後の郵便料金改定予定
2021年7月の時点において、定形郵便やハガキなどの郵便料金については改定予定はありません。
しかし、速達料金については、2021年10月1日以降、現行の料金から1割程度引き下げとなることが発表されています。
郵便物が料金不足の場合どうなる?
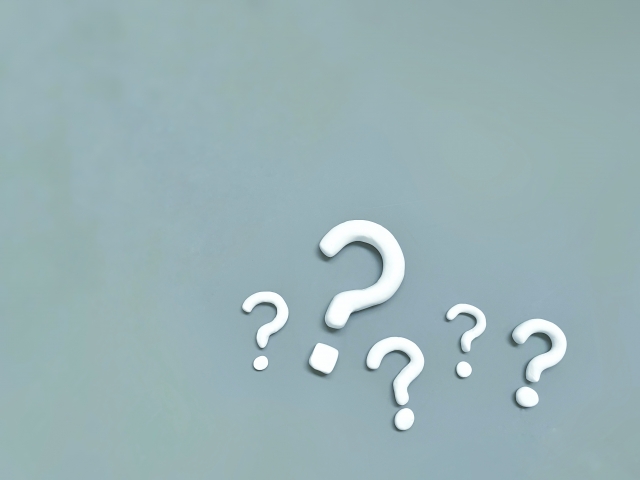
仮に郵便料金が改定されたことを知らず、従来の料金の認識のまま切手を貼ってポストに投函した場合、料金不足で正しく配達されないことが考えられます。
そのようなとき、郵便物に差出人の氏名や住所が記載されていれば郵便局から差出人へ「料金が不足しています」などのメモと一緒に返送されます。
しかし、差出人の情報が記載されていなかったり、差出人の住所と集配管轄エリアが異なっていたりする(差出人住所が東京都で、集配管轄エリアが埼玉県など)場合には、宛名に記載された受取人に配達され、受取人に対して不足額が徴収されます。
しかし、受取人によっては受け取りを拒否することも考えられ、差出人の住所も分からないと「還付不能郵便」として郵便局員によって中身が開封されるケースがあります。
開封したときに差出人の情報が判明すれば返送されますが、中身を確認しても差出人が不明の場合、以下のパターンごとに対応が変わってきます。

有価物で滅失・き損の恐れのある郵便物
宝石や商品券などの有価物は、ただちに売却手続きが行われ、売却代金の1割に相当する額を日本郵便が手数料として徴収します。
残りの売却代金については日本郵便で1年間保管されますが、保管期限を過ぎても請求者が現れない場合には日本郵便へと帰属します。
そのため、有価物を郵送する際には、差出人の情報を必ず記載するようにしましょう。
有価物ではない郵便物
個人に宛てた手紙など、有価物にあたらない場合には、日本郵便で3ヶ月間保管されます。
その後、3ヶ月を過ぎても請求者が現れない場合には郵便物が廃棄されてしまいます。
▶︎クアディエントの郵便料金計器で総務や経理のお悩みを解決!詳細はこちら
郵便物の料金不足の処理は郵便局員次第
もともと郵便は公共性の高いサービスであるため、仮に郵便料金が不足していた場合、郵便局員の中には配達を優先してくれるケースもあります。
しかし、速達ではなく差出人の情報も記載されている場合には、料金不足によって差出人に戻ってくる可能性も十分考えられます。
郵便物の特性や郵便局員の判断によっても状況は変わってくるため、上記で紹介した内容はあくまでも参考程度にとどめておきましょう。
もっとも重要なのは、料金不足にならないよう、あらかじめ情報を調べておくことです。
どうしても不安であれば、郵便局の窓口に持ち込んで計量のうえ正確な料金を支払うよう方法が確実です。
▶︎事務や総務部門の郵便業務を効率化するには?課題に対応した方法例を解決
料金不足の郵便物が届いたときは?
差出人の立場としてではなく、受取人の立場で考えた場合、ある日突然料金不足の郵便物が届き、不足分を請求されることも考えられます。
そのような場合、受取人はどう対処すれば良いのでしょうか。
不足分の料金を支払い郵便物を受け取る
あらかじめ郵便物が届くことを知っている場合には、受け取りを優先するために料金の請求に応じ、支払うことがおすすめです。
特に仕事に関係する重要な書類や、購入した商品などの場合にはいち早く受け取らなければなりません。
不足分の料金を支払う方法としては、通知はがきに不足分切手を貼り郵送する方法と、郵便局に通知はがきを持参して支払う方法があります。
不足金額が少額の場合は郵便物と一緒に通知はがきが配達されますが、100円以上の不足額がある場合には不足分の支払い確認がとれてから配達されます。
もし急ぎで郵便物を受け取る必要がある場合には、保管されている郵便局へ通知はがきを持参するとスムーズです。

受け取りを拒否する
差出人が不明であったり、到着予定のない郵便局物が料金不足によって届いたりした場合には、受け取り自体を拒否することも可能です。
通知はがきの「この郵便物は、料金が不足していますので受け取れません」という項目へチェックを入れ、サインまたは捺印のうえポストへ投函してください。
ただし、郵便物を開封してしまった場合には受取拒否ができないため注意しましょう。
▶︎特定記録郵便はどんな制度?郵便局での出し方や注意点も解説
差し出し後に郵便物の料金不足に気付いた場合の対処法

郵便物を差し出した後、自身で料金不足に気付いた場合、郵便局に対して「取り戻し請求」という手続きを行えばキャンセルが可能です。
ただし、取り戻し請求のタイミングによっては手数料が発生する可能性もあるため注意が必要です。
郵便物はポストへ投函後、エリアごとに設置されている集配局とよばれる郵便局へ集められ、その後宛先の最寄りの郵便局(配達局)へ配送されます。
郵便物がポストから集荷される前、または集配局にある段階であれば、取り戻し請求の手数料はかかりません。
しかし、すでに配達局へ到着済みで、宛先への配送待ちの状態になっている場合には、以下の手数料を支払わなければなりません。
- 配達局から取り戻し請求した場合:420円
- 配達局以外の郵便局から取り戻し請求した場合:580円
ちなみに、取り戻し請求の手続きにあたっては、本人確認書類および印鑑(認印)を持参する必要があります。
料金不足の郵便物を放置したらどうなる?
通知はがきとともに料金不足の郵便物が届いたものの、料金を支払わず受取拒否もしないまま放置しておくと、郵便局から再度通知はがきが届くことがあります。
長期間支払わずに放置していた場合、何らかの罰則がついたり、郵便局から訴えられたりといったケースは極めて稀のようですが、受取拒否をしない以上は受取人が不足額を支払う必要があるため、できるだけ早めに支払うようにしましょう。
▶︎クアディエントの郵便料金計器で総務や経理のお悩みを解決!詳細はこちら
まとめ
郵便料金は消費税増税などのタイミングで改定されており、それに気づかないまま切手を貼ってポストに投函してしまうと、料金不足によって相手先に届けられない場合があります。
また、受取人に対して不足額が請求されてしまうため、当事者間でのトラブルやクレームに発展する可能性も考えられます。
今回紹介した内容を参考に、郵便物を発送する際には十分注意して過不足なく料金を支払うようにしましょう。

